メガネのことやメガネ店のことを、少しでも身近に感じていただきたい。悩みを気軽にご相談いただいて、1人でも多くの方に快適な毎日を送っていただきたい。
そんな想いでさまざまな企画をお届けしていますが、今回は補聴器座談会の様子、第2弾をお送りいたします。
※前回の記事はこちら。

今回は、最近の補聴器がどれだけ小さくなっているのか、ご紹介したいと思います。
「補聴器って、つけているのが目立って恥ずかしい…」と思っていませんか?聞こえに不安のあるご家族に勧めたくても、「あんな目立つもの、嫌がるのでは…」と思うと、なかなか難しいですよね。
でも、それって一昔前の補聴器のイメージかもしれません。最近の補聴器は小型化していて、本当に目立たないんです。
この記事では、前回の座談会にも参加いただいた宮良さんと水落さんのご協力を得て、補聴器を実際に装着したときにどれだけ目立たないものなのか、写真付きでご紹介していきます。
さらに、ご家族に補聴器を勧めるにはどうしたらいいか、補聴器のプロであるお二人に聞いてみました。「補聴器をつけてほしい」とまっすぐ伝えても、ご本人が嫌がることも少なくないでしょう。ご家族もご本人もみんな快適に過ごせるように、参考にしていただけたら幸いです。
目次
今の補聴器の「小ささ」、ご存知ですか?
補聴器を実際に店頭などで見たことのある方は、どのぐらいいらっしゃるでしょうか?「よく見たことがない」という方も多いのではないかと思います。
補聴器にはさまざまな種類があります。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

補聴器をつけていることが最も目立ちにくいには、耳の穴に直接装着する「耳あな型」です。とはいえ、いかにも「耳に何か入れている」感じに見えるのはできるだけ避けたい…と思う方もいらっしゃるでしょう。
実際の耳あな型補聴器をいくつか見せていただきました。比較のために、横にスマートフォンを並べています(画面の部分が約9cm)。

5種類の補聴器を並べてみました。最も小さいもので、先端まで3cm程度です。同じ耳あな型補聴器でも、機種によって大きさに差があるのがおわかりいただけるかと思います。
とはいえ、こうして見せられても「実際につけたときに目立つのかどうか」はわかりにくいですよね。そこで、宮良さんにモデルになっていただき、実際に補聴器をつけたとき外からどのように見えるのか、確かめてみました。
「人からどう見えているかって、わからないですからね」と、快くモデルになってくださった宮良さん。本当にそうなんですよね…!
先ほどの5種類の中で最も小さい補聴器をつけると、こんな感じです。

補聴器をつけていること、わかりますか?パッと見ただけではほとんど気づかないレベルではないでしょうか…?
もう少し近づいて見てみます。

よく見ると、先端の部分がちょこんと出ているのが見えます。でも、このぐらい近づかないとほとんどわからないということ。今の補聴器って、こんなに目立たないんですね…!
こちらは、先ほどの5種類のうち、3番目に大きい補聴器。

さすがに少し「補聴器らしさ」を感じるようになりますが、それでもずいぶん小さいですよね。この写真は少し後ろから撮影していますので、補聴器の存在がよくわかりますが、角度によってはかなり目立ちにくいはずです。
そして、5種類のうち最も大きい補聴器をつけると、こんな感じです。

「補聴器」と聞いたときに多くの人がイメージするのは、このサイズのものではないでしょうか?
ここまで来るとさすがに「補聴器をつけているな」という感じが外からもわかりますが、逆に言うと、「ここまでの大きさでないと補聴器は目立たない」ということでもあります。
機種によって大きさは異なりますが、ご覧のように補聴器はかなり小型化が進んでいます。「補聴器は目立つから恥ずかしい」とは言い切れないんですね。
恥ずかしさで不便を我慢するぐらいなら、小さな補聴器を選んで快適にお過ごしいただきたい…と私たちは思うのです。
小さいからこそ生まれる不安も解消!
小さな補聴器は、つけたときに目立たないことがメリットですが、小さいからこそのデメリットも存在します。しかし、デメリットを解消するための工夫もいろいろとされているんです。
小さいとなくしやすい?
小さい補聴器は、落としたりしても気づきにくく、なくしやすいというデメリットがあります。「なくすのが嫌だから」と外につけていかない方もいらっしゃるそうですが、それでは本末転倒になってしまいますよね…。
→紛失防止のためのチェーンがあります
メガネを首から下げるチェーンはよく見かけますが、実は補聴器用のチェーンもあります。クリップで襟元などに留めることで、万一耳から落ちてしまっても紛失しなくて済みます。
→万一のための保証制度があります
紛失してしまった場合のために、保証制度を用意している販売店もあります。内容や範囲は販売店ごとに異なりますので、購入時に相談しておくと安心ですね。
操作しにくい?
小さな補聴器の場合、小さい分、本体の操作がしにくくなってしまうデメリットがあります。
例えば電池交換。本体が小さければ電池も小さくなります。補聴器を使用するのは年齢の高い方が多いこともあり、細かい操作が難しい方も。「自分で電池を換えられないから使えない…」と思われる方もいらっしゃるようです。
しかし、電池を交換しやすいようにメーカーも工夫しているんです。小さな補聴器の電池交換の様子を、水落さんに見せていただきました。
92歳のお客様も、これで電池交換できたそうです。
簡単に電池を出し入れできる道具が付属しているんですね…!
まさに百聞は一見にしかず。「扱えないのでは…?」と思い込んでいるよりも、実物に触れてみるのが早いですね。
最新の補聴器を家族に試してほしい!と思ったら?
いくら補聴器が進歩しているとわかっても、聞こえに不安のあるご家族に対して「補聴器を使ってほしい」と直接伝えるのは難しいものです。「そんな年齢ではない」「必要ない」などと言われてしまうこともあるでしょう。
でも、補聴器があれば、コミュニケーションも円滑になりますし、聞こえが改善することで明るく活発になる方も多いのです。
そこで、「家族に補聴器を使ってほしい」「お店に行って試してみてほしい」という方のために、抵抗なく補聴器を試してもらえる誘い方実例を、プロのお二人に聞いてみました。
水落:
自分だけが補聴器を勧められてしまうと、ご本人様は警戒してしまうと思うんです。例えばお父様に補聴器をつけてほしいからと言って、お父様だけに補聴器を勧めると、「なぜ自分だけ?」「聞こえないと思っているのか」「年寄り扱いするな」と思われがちです。
ですから、「ご家族様みんなで聞こえの検査を受けにいく」というのが1つの方法だと思います。お父様だけでなくお母様やお子様も、「みんな検査を受けるからお父さんもどう?」という感じで。
宮良:
「耳の健康診断をしてくれるから行ってみない?」という気楽な感じですよね。
水落:
アイメガネ店舗では「目のストレス測定会」というのを定期的にやっています。以前テレビでも紹介された「アコモレフ」という機械を使ったストレスチェックです。目のチェックには皆さま抵抗が少ないようで、気軽にお越しくださいますので、そのついでに聞こえ方を調べるのも良いですね。
ーーなるほど、「目」を入り口に「耳」も調べるということですね。メガネの方が補聴器よりもハードルが低い。そういう意味では、ご家族様としても眼鏡店の方が誘いやすいかもしれません。
宮良:
補聴器専門店は専門店だからこそ、「敷居が高い」という感覚をお持ちの方も多いようですね。眼鏡店の方が敷居が低くて相談しやすいと感じてもらえるようです。メガネは若い頃から使っていらっしゃる方も多いですし、年齢を重ねた後でも補聴器よりは相談しやすいでしょう。
前回も似たようなお話をしましたが、眼鏡店であればだいたい7〜8時まで開いていますし、土日も営業しています。ご家族様が仕事から帰ってきた後やお休みの日に、一緒に相談いただけます。そういう点でも、眼鏡店はお越しいただきやすいのではないかと思います。
補聴器は貸し出しサービスを行っていますが、貸し出しサービスを利用された方のうち、実際に購入されるのは半数程度ではないでしょうか。レンタルしたからと言って買わなければいけないものではありませんので、まずはどんなものなのか、気軽に試していただきたいですね。
編集後記
補聴器の技術はどんどん進歩しています。だからこそ、試さずに先入観だけで補聴器を使わずにいるのはもったいないことだな…と改めて感じました。
大切な家族にはやっぱり元気で長生きしてほしい。今回取材を行った私自身もそう思います。ですから、聞こえを補聴器で補い、楽しく会話ができる状態を取り戻すことは、「元気で長生き」のためにとても大切だと思うのです。
この記事を通して補聴器について少しでも知っていただき、大切な方をサポートするために知識を活用いただけたら嬉しいです!
【記事監修】アイジャパン株式会社 ビジョン&ヒアリングケア事業部 木村幸生


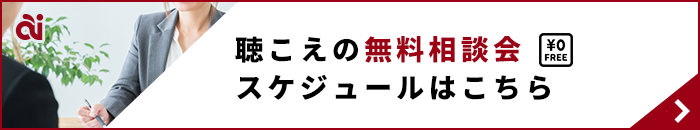



コメント